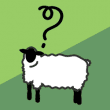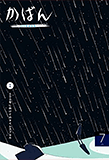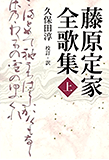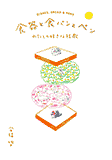小野茂樹『羊雲離散』を読む

さまよえる歌人の会とは?
「さまよえる歌人の会」は2007年の1月にスタートしました。2006年の終わり頃、何かの会の二次会でたまたま近くの席になった内山晶太さん、多田百合香さん、石川が、「歌集を読む勉強会があったらいいよね!」と盛り上がり、勢いで結成したのが始まりです。
開催は月に一度。月末の土曜日の17時半~21時過ぎまでというパターンが多いですが、他のイベントとの兼ね合いで、多少日程をずらすこともあります。場所は、基本的には東京都内(浜松町、渋谷、月島など)の会議室です。
現在は石川が会場予約・メール連絡係、牧野芝草さんが二次会係を担当していますが、代表者、主催者といった立場の人はいません。参加人数は、多い時で30名以上、少ない時で7~8名。やや少なめの方が議論は白熱しますが、大人数でわいわい喋るのも楽しいものです。1年間ほぼ皆勤の人がいる一方で、はじめましての人や、数年ぶりにひょっこり顔を出してくれる人もいたりして、顔ぶれがどんどん変わっていくのも特徴です。

勉強会の流れ
勉強会ってどんなふうに進めればいいの?と、たまに聞かれます。いろいろなやり方があると思いますが、さまよえる歌人の会の場合は、
- (1)事前に指名されたレポーター2名がレジュメを用意し、順番に発表
- (2)レポーターへの質問・意見
- (3)フリートーク
- (4)「私の好きな一首」を全員が発表
- (5)次回以降の予定(歌集・レポーター決め)と、出席者による告知・宣伝
という流れで進んでいきます。フリートークの部分は、司会が指名することもありますが、言いたいことがある人はどんどん発言してOKです。
その月にどんな歌集を取り上げるかは「行き当たりばったり」が信条。誰かが「最近のイチオシ」を紹介してくれたら、それに乗っからせていただきます。最近出たばかりの話題の歌集と、半世紀以上前の歌集を行ったり来たりすることも珍しくありません。2014年はこれまでのところ、
- 1月:五島諭『緑の祠』&陣崎草子『春戦争』(新鋭短歌シリーズ第1期)
- 2月:鯨井可菜子『タンジブル』&堀合昇平『提案前夜』(新鋭短歌シリーズ第1期)
- 3月:望月裕二郎『あそこ』&木下龍也『つむじ風、ここにあります』(新鋭短歌シリーズ第1期)
- 4月:田谷鋭『乳鏡』
- 5月:小野茂樹『羊雲離散』
- 6月:堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』
- 7月:佐佐木幸綱『群黎』
- 8月:大松達知『ゆりかごのうた』
というラインナップで進んでいます。
番外編として、9月には恒例の「さまよえる合宿」を開催。恐ろしくも楽しい合宿については、いずれこの連載のなかでご紹介したいと思います。年末には、その年の新人賞(歌壇賞、短歌研究新人賞、角川短歌賞)作品をまとめて読み返しています。
さて、次の項からは、いよいよ勉強会で読んだ歌集をご紹介していきます。
小野茂樹『羊雲離散』
小野茂樹という歌人をご存知でしょうか。歌集は読んだことがなくても、
- あの夏の数かぎりなきそしてまたたつた一つの表情をせよ
の一首ならば知っている、という方は多いかもしれません。
小野茂樹は1936年生まれ。中学校の頃に短歌を作り始め、早稲田短歌会や歌誌「地中海」などで幅広く活躍していました。1968年に第一歌集『羊雲離散』を刊行し、翌年、同書で第13回現代歌人協会賞を受賞しましたが、1970年、交通事故のため33歳の若さで急逝しています。
『羊雲離散』(よううん・りさん)は、17歳から29歳までの作品を収めています。恋と失恋、早稲田大学入学と中退、結婚と別居、初恋の人との再婚といった、激動の青春期を詰め込んだ一冊。〈あの夏の…〉以外では、
- 五線紙にのりさうだなと聞いてゐる遠き電話に弾むきみの声
- 感動を暗算し終へて風が吹くぼくを出てきみにきみを出てぼくに
- 鬼やらひの声内にするこの家の翳りに月を避けて抱きあふ
といった、ビビッドな相聞歌が人口に膾炙しています。
さまよえる歌人の会で取り上げたのは今年の5月。レポーターは、増田一穗さん(無所属)と澤田順さん(かばん)。司会は今井聡さん(コスモス、桟橋)、参加者数は16名でした。
「ドラマ性」と「内面に忠実な表現」
増田一穗さんのレポートは、小野茂樹の短歌が持つドラマ性と、感覚や内面に忠実であろうとする表現方法について、緻密に読み解いていく内容でした。
ドラマ性については、
- まなざしも眼もわがものと誓はせしその夕べより怖れられしか
- 強ひて抱けば我が背を撲ちて弾みたる拳をもてり燃え来る美し
1首目の独占欲、2首目の追い打ちをかけるような下の句などに見られる「強い表現」をキーワードとして挙げていました。
内面性については、
- 薄き紙に境してわれら破らむと焦ればきみの去る足音す
- いだきあふわれらの内に粉のごとく軋めるもののありと声呑む
- 前肢のごとき岬をめぐりつつ海より遠きもの見え来たる
などの歌について、「薄き紙」「粉のごとく軋めるもの」をわかりやすいモノに置き換えず、感覚に忠実なまま歌に流し込んでいること、「海より遠きもの」のように見えないもの(抽象的な概念?)を詠む傾向があることなどを指摘しました。実は『羊雲離散』には、読んでいて「ん?これどういう意味?」と立ち止まってしまう歌が意外と多いのですが、増田さんの整理で、その「わかりにくさ」の正体が少しわかったような気がします。
光と闇のコントラスト
一方、澤田順さんは、『羊雲離散』の「光」と「影」の表現に注目しました。
- 髪いぢる手に光ありわが前にきみただ明日のひととして立つ
- ほしいまま朝のひかりの波うてる廊下よ娶りの日の遠からず
- 坂の上はさへぎりもなき夕映のまた失ヘば得がたきひかり
澤田さん調べでは、全189首中「光」「ひかり」という単語が単独で出てくる回数は38回。これは動詞や熟語を除いた数字ということですが、かなり多いと言えるのではないでしょうか。澤田さんは、光の動きを凝視する歌に秀歌が多いとした上で、「一回性のもの、時間と共に過ぎ去るものだからこそ、小野茂樹は光を多用したのではないのか」と指摘しました。「光」という単語こそ使われていませんが、初めに挙げた、
も、光あふれる夏のイメージと、「あの」で示される一回性が歌のカギになっているのでは、とのことでした。
なお、「光」の対義語である「闇」の単独使用は23回、光(明るいもの)と闇(暗いもの)の両方が出てくる歌は25首以上。小野茂樹が、一度きりの生と、その対極にある死のコントラストに注目する歌人だったことがよくわかります。
フリートークは言いたい放題
フリートークで出た意見を、項目ごとにまとめてみます。
■ 相聞と独りきりのわたし
- 相聞の歌は粘着質。自意識過剰
- 相聞というより、自分の身体がどう他人と接触するかに興味がある
- 相手を歌うのではなく、相手を想う自分を歌っている。独りきりの感覚が強い
- 登場人物が少ない
- 父親への屈折した思い
- 実は社交的な人だったらしい。意外!
■ 文体
- 二重否定が多い
- 意外と「結句がっかりパターン」が多い
- 結句8音成功しているか?
- 言葉の選び方(和語と漢語の混ざり方)が気持ち悪い
■ わかりにくさと時代性
- 〈あの夏の…〉の印象が強かったが、意外とわかりにくい歌、観念的な歌が多い(一首のイメージと歌集単位で読んだときのイメージが違った)
- 〈あの夏の…〉もそうだが、さっと読んでわかるのに後でよく考えるとわからなくなってくるのが、名歌の証。ちょっとギアを落として読んだ方がいい
- 小野茂樹は奥村晃作さんと同い年。飢えや疎開なども経験している世代だろう。時代性を考える必要がある
- 先行する歌人の影響もあるのでは(春日井建、大西民子、三国玲子など)
- 編年体で、終盤の「あはれ青春」辺りから俄然読みやすくなる。具体化の方法に変化が?
えーと、こうして書き出してみるとなんだか言いたい放題で、小野茂樹に若干申し訳ないような気持ちになってきますが、いろいろな角度から意見が出て楽しかったですし、「これまでと印象が変わった!」という人が多かったのは、素直に良かったと思います。
連作「坩堝」の謎
「時代性」に関して、今回、私が個人的に面白かったことがありました。次の歌を読んでみてください。
- さきがけて喬き木の葉はそよぎつつ谷騒ぐとき静けしすでに
- 見下ろしのみどりは宙に崖を埋めこの虚しさは谷のむなしさ
- ひとりにかへりし時の地の広さ火器捨てし兵は生き得ざりしや
- 散りぢりに河面に映り別れゆきとどまるものは水に石擲つ
1~2首目は「坩堝」という連作から、3~4首目は「礫と薄明」から引きました。これらの歌に共通するテーマは何か、わかりますか?
手がかりになるのは、篠弘『現代短歌史3 六〇年代の選択』の「小野茂樹と佐佐木幸綱」の項です。とても面白い項なので、興味のある方はぜひ全文を読んでいただきたいのですが、ここでは、ほんの一部だけ引用します(括弧内は石川注です)。
小野が、揺れ動く安保問題に無関心であったかというと、けっしてそうではなかった。(中略)「坩堝」のほうは、くりかえされた闘争の場が、喩によって、まさに〈崖深い谷〉としてよまれる。(中略)しずかになった谷底をみつめ、いっそう〈虚しさ〉を噛みしめていたのである。(中略)
こうした抽象化をはかり、かつ喩を活用した方法は、いちじるしく清原(日出夫)・岸上(大作)の安保詠と異なっていた。(中略)小野は、一見闘争をよんだとは思えないようなスタイルで、生きる悔しみや虚しさをさぐっていたことになる。
篠さんの解説によれば、小野茂樹は、学生運動のさなかに自死した岸上大作の作品と自らの作歌意識を照らし合わせた上で、岸上のような直叙(=想いを率直に述べること)の方法に懐疑を覚え、「詩的造形性」や「論理」を抱き込む短歌のあり方を試みていました。つまり、「坩堝」や「礫と薄明」は、60年代の学生運動が終わった後、その挫折感を直接述べるのではなく、抒情詩として昇華させようとした連作、である可能性が高いわけです。
……いやー、わかんないわー、それ。
と、ツッコミたくなるのも、自然な反応なのではないでしょうか。小野茂樹がやろうとしていた非常に繊細な闘いは、同時代の読者にさえ理解しにくかったし、時を経た現在では、さらにわかりにくくなってしまっています。かくいう私も、「礫と薄明」はともかく、「坩堝」の方は全く時代性を読み取れませんでした。ただ、「坩堝」の不思議な暗さ、ただ崖のことを描写しているにしては奇妙にわだかまりのある物言いが、心に引っかかったのも確かです。
それでは、読者である私は、ある短歌と向き合うとき、その歌が作られた時代背景や作者の制作意図を、どこまで知るべきなのか。また、短歌の実作者である私は、時代や社会をどのように詠み込んでいけばいいのか。まあ、はっきり言って正解なんてものはありませんし、向き合う作品のタイプによって読み方は変わって良いものだと思いますが、『羊雲離散』は、そんなことをあれこれ考えるためのヒントをくれたのです。
「私の好きな一首」コーナー
ちょっと小難しい話になってしまいました。最後に、出席者が「私の好きな一首」として挙げた歌から幾つか引用したいと思います(矢印以下は選んだ人の一言コメントです)。
- 洞のごとき夜道にわれを追ひ抜ける犬の尾白しうしろ足まで
→ ぱっと(心に)入ってきた歌 - 運び来てしばらく暗き蝋燭にいろ濃きひかり生まれたる見つ
→(時代によって)消耗しない歌 - くぐり戸は夜の封蝋をひらくごとし先立ちてきみの入りゆくとき
→ 歌集中で一番色っぽい。「灯」には「光」と違う意味(内面性?)がある - 囲はれし園もたがはず冬なりきしきりに波紋の浮かぶ池あり
→ マトリョーシカっぽい - 強ひて抱けばわが背を撲ちて弾みたる拳をもてり燃え来る美し
→ 起こることを次々と動詞で畳みかける。モテそう - 青林檎かなしみ割ればにほひとなり暗き屋根まで一刻に充つ
→「屋根」はちょっと盛ってるけど、この過剰さはキライじゃない
会の雰囲気が少しでも伝わったでしょうか。次回以降も、さまよえる歌人の会で読んだ歌集をご紹介していきます。

さまよえる歌人の会へのご参加・お問い合わせは、石川美南 shiru@m13.alpha-net.ne.jp まで。連絡用のメーリングリストをご案内します。次の通常回は10月25日(土)。取り上げる歌集は、木下こう『体温と雨』です。